
|
|
不思議な世界私が取材した不思議な話です。本になりました。 超能力者・霊能力者に学ぶ不思議な世界の歩き方  不思議な世界 (その1) 今泉が見た龍 龍を見た男がいる。ラグビー元日本代表のフルバック今泉清だ。その巨大な龍は大地から立ち昇っていた。だがそれが見えるのは、今泉だけ。そのことを信じる者もなく、今泉はいつしか「変人」「宇宙人」のラガーマンと呼ばれるようになった。 その「変人」が早稲田大学ラグビー部四年生だった1990年。伝統ある早明戦のことだ。残り2分で12対24と明大がリード。明大の勝利は揺るがないかにみえた。しかし、早稲田が反撃する。6点差にした後のロスタイムに、今泉がボールを受けとると自陣から60メートルを独走。同点につながるトライを決めた。今でもラグビーファンの間で語り草になっている劇的な試合だった。そのときのことを今泉は、自分の走るコースに「光の道を見た」と証言している。 この今泉の不思議な体験は、常人にはなかなか理解できない話だ。一流のスポーツ選手はもともと、超常的な力をもっている。しかし今泉の能力は、スポーツ選手のそれというより、霊能力者の能力に近い。今泉自身、そんな自分に戸惑いを覚えていたらしく、シャーリー・マクレーンの『アウト・オン・ア・リム』を読んでやっと、「自分だけではないんだ」と思うようになったという。 今泉が見た龍は何だったのか。思想家中沢新一の『精霊の王』には、「千日行」を成し遂げた蹴鞠の名人藤原成通(1097年生)が鞠の精たちに出会った話が紹介されている。「芸能の達人たちはこの神=精霊の実在を、超感覚的ないしは直感的にとらえているように思える。つまり、自分の身体や感覚を、三次元の物質で構成された空間を抜け出して、そこに守宮神が住むという柔らかく律動する特殊な空間の動きを自分の身体の動きや声の振動をとおして、観客の見ている普通の世界の中に現出させていこうとしたのである」と中沢は言う。 グラウンドから湧き上がるように立ち昇ったという龍は、今泉が見たラグビーの精龍であったのだろうか。 (その2) 龍神と翁 「この岩の向こうに天の真名井がある」――。そのとき高畠吉邦(元天神人祖一神宮管長)は、心の奥にまで響く龍神の声を聞いた。高畠はそれが間違いなく龍神であったと言う。その声の指示に従って、洞窟から外に出て探してみると、そこには確かに丸くくりぬかれた岩があり、水をたたえていた。それを見た瞬間、高畠はそれが「天の真名井」であることを確信したという。 高畠吉邦は、謎の古文書「竹内文書」を世に出した竹内巨麿(天津教教祖)の四男だ。霊感が強く、幼少のころより釜鳴りの神事などを司っていた。理工系の大学を出た後、造船事業や自動車修理業などをしていたが、戦後何年か経ったあるとき(戦後天津教はGHQから活動停止処分を受けていた)、竹内文書に記されている天柱石(富山県平村)を訪ねてみようということになった。 吉邦は車を運転、妻澄江や知人らとともに五箇山の山中に分け入り、天柱石を探した。ところが山道は曲がりくねり、まるで迷路。そこへ道端を歩いている翁と出くわした。吉邦が道を尋ねると、その翁は「ちょうど天柱石の方へ行くところだから、ご案内しましょう」と言う。吉邦ら一行は、その翁を車に乗せ、天柱石へと向かった。 車内はギュウギュウ、道は悪路であったが、翁の案内で何とか無事に天柱石にたどり着いた。天柱石は、天にも届けとばかりに空に向かって突き出た高さ50メートルほどの船形の巨大な奇岩である。吉邦らはその異形に興奮し、翁と澄江を置いて天柱石のそばに駆け寄り、周りを調べ始めた。 不思議なのは翁であった。後に残された澄江は、翁に謝礼をするためにお金を包もうとしてちょっと目を離し、再び顔を上げたところ、翁の姿は忽然と消えていたのだ。ほんの数秒前まで、すぐそばにいた翁がいない。澄江はあっけにとられた。 翁は誰であったのか。思想家中沢新一によると、神話学や芸能の世界では翁は守宮神(宿神)にほかならないという。しかしそれは、あくまでも神話や芸能における象徴としての翁である。現実の世界に翁となって現われる宿神など本当にいるのだろうか。 一方吉邦は、翁が煙のように消えていなくなったことも知らずに、天柱石の横にある洞窟に入っていた。吉邦はその洞窟で、冒頭の「龍神の声」を聞いたのだ。 竹内文書によると、天柱石は宇宙と地球、天と地をつなぐ、いわば神霊界の出入り口であったという。現実と神話が交わるところに龍神は現われる。吉邦らを天柱石へと導いた翁は、宿神の化身であったのだろうか。 (文中敬称略) (その3) 位山の龍神1 ダナ平林道終点の駐車場には、一風変わったモニュメントがある。一九八四年に地元の仏師、都竹峰仙が造ったジェラルミン製の球体でできた「太陽神殿」だ。 私が初めて位山(岐阜県宮村)に登った一九八四年秋には、既にこの神殿は完成していた。当時はこの神殿ができた経緯をまったく知らなかったため、新興宗教の教団かなにかが、この土地を買って神殿を建てたのかと思ったほど奇異なモニュメントだ。しかし、実際にこのモニュメントができたいきさつを聞いてみると、非常に興味深い話であった。都竹峰仙は亡くなっているが、息子の都竹昭雄氏が著書『飛騨の霊峰位山』で、その由来を詳しく語っている。 それによると、すべては都竹峰仙が子供のときに体験した神秘体験から始まったようだ。一九一一年に岐阜県高山市三福寺で生まれた峰仙は、小学校を卒業後、一三歳で宮大工になろうと決心。弟子入りして飛騨各地の寺の造営に携わり、寺の欄間を彫ったりするかたわら、独学で彫刻を学んだ。 一九三二年ごろ、御嶽教飛騨教会で新しい不動明王を製作しようという話になった。御嶽教の行者が神示を受けたところ、折(お)敷地(しきじ)(岐阜県大野郡丹生川村(にゅうかわむら))の山中にある直径六尺の栃の木を使い、峰仙という者に不動明王を彫らせよ、とのお告げがあったそうだ。行者は峰仙という彫刻家も、そのような栃の木が山中にあることも知らなかったが、方々を探してやっと若い彫刻家峰仙と見事な栃の木を探し出した。 白羽の矢が立った峰仙には、子供のころから不思議な体験があった。夢の中で何度も不動明王が出てきたのだという。その姿を峰仙は、栃の木に刻み込んだのだ。白装束で身を清め、三六五日間、刻み続けた。完成したのは一九三五年、峰仙が二三歳のときだった。 それが現在、高山市七日町の不動橋近くにある御嶽教飛騨教会に鎮座している栃目不動明王だ。身の丈四メートル八〇センチ、背中の火炎部分を入れると七メートル以上もある。ギョロリとむいた大きな目玉、右手には剣を、左手には羂索(けんざく)を持つその迫力は、初めての作品とは思えない出来栄えで、霊験あらたかな不動明王であるとしてすぐに評判になったという。 峰仙はその後、東京で本格的に彫刻の修行をし、戦後高山市に戻ってきた。 そして、本当に不思議なことは一九五三年に起きた。位山を開きに来たという関西の人たちを位山に案内した後、彼らが原因不明の奇病にかかってしまった。何件かの病院で診察を受けたがまったく原因がわからない。ところが、ある有名な霊能者に相談したら「位山を案内した人こそが位山を開く人だ。その人に祈願を立てて祈ってもらえば病気は治るだろう」と言われたというのだ。 (その4) 位山の龍神2 半信半疑のまま五三年一一月、峰仙は位山に登った。頂上付近の手前で峰仙は「位山を守護している大龍神よ、われを使ってこの霊山を開けたもうなら姿を現したまえ」と祈願を立てた。すると、巨大なエネルギーを感じて全身がしびれたかと思うと、足元より大龍神が立ち昇り、「位山を開け、永年待ったぞ」という大音声が峰仙の耳に響いた。 峰仙は「私は彫刻家であり、行者のような修行もしていません。位山を開くような大それたことは遠慮させていただきたいと思います」と答えると、その声は「それはならんぞ。位山を開く時が来たのだ。それがそなたの運命だ!」「頂上の巨石の扉を開くのだ。天から指示をするからそのとおりやればよい。まず六つの法を降ろす。それを六ヵ月で学べ。そして最後の三日三晩は山に籠もり位山を開け!」と告げたという。 その言葉どおり峰仙は、神示により陰陽の原理、風の法、火の法など六つの法を学び、とうとう五四年八月、位山の頂上に三日三晩籠もり、夜を徹して行を続けた。すると明け方五時半ごろ、巨石の間から巨大な火柱が天に向かって昇り、位山全体が真っ赤に染まった。こうして位山は開かれ、「日の大神様が太陽巨石の扉を開けて世に出られた」ことを知ったという。 これを受けて峰仙は、位山のご神体の制作にとりかかった。位山のヒノキの神木を使って天照日の大神のご神体を作り、五五年に位山頂上付近の巨石の横に神殿を建立した。しかし、この場所は位山の神々を祭る場であり、あまり足を踏み入れたくないという考えや、「新しく球体の神殿を造るように」という神示があったため、八四年に球体の太陽神殿が七合目に設置されたのだという。 位山には昔から大蛇が棲むという言い伝えがあり、地元の人でもあまり踏み込むことのない神聖な山だったという。峰仙が見た龍神こそ、位山の守り神であったのか。なぜ今の時代に位山を開く必要があったのか。 私たちの目に見えない世界にはおそらく、ある一定の方向に流れる大きな力(意志)が存在するのだろう。峰仙が位山を開いた六年後、今度は神道家・金井南龍が台風の風が吹き荒れる中、白山に登り、白山神界の封印を解いたのだという。一九六〇年八月九日のことだ。『神々の黙示録』(徳間書店)によると、そのとき南龍は、白山神界の菊理姫の働きを元に戻すと同時に、天皇一族に殲滅された白山王朝(縄文系の王朝とみられる)の歴史を霊視する。私がホームページで使っている白山菊理姫はここから取っている。 (その5) 龍神に出会った人々 龍神に出会ったという人は意外に多い。漫画『エースをねらえ!』の作者山本鈴美香もその一人だ。記憶は定かではないが、確かどこかの神社で巨大な龍神を見てから巫女になったようなことを雑誌に書いていた。 ときどきテレビに登場する国際気能法研究所の秋山眞人も龍神を見たことがあると言う。秋山が見た龍神は空を飛んでいた。呼びかけると返事をしたという。「おそらく、この空間には目に見えない因子のようなものがあって、それが人間の額にぴたりとくっつくと、その因子が持つ影像が見えるのではないか。私が見た龍は、恐竜か何かの因子がたまたま、おでこに付いたために、まるで龍神が姿を現したように見えたのではないか」と秋山は言う。 秋山の仮説は興味深い。そういえば以前、岩手の座敷童(ざしきわらし)を撮ったとみられるテレビ局の映像にも、丸くて小さい光の玉が映っていた。これが霊界の因子であろうか。この因子には情報が入っていて、それにアクセスできる霊能者ならば、そこから映像を含む情報を取り出すことができるわけだ。 秋山は夜間、山の中を歩いていて七福神にあったこともあるという。「まさか、七福神は空想の産物ではないか」と、私が聞き返すと、ただ笑っていた。漫画家の水木しげるはかつて、「妖怪は人間による想像の産物ではない。目に見えない不思議な世界に実在する妖怪を、人間が持つ霊界アンテナのようなものでキャッチしてしまうのだ」という趣旨のことを話していた。そうだとすると、人間が想像したとされる妖怪も、龍神も、七福神も、実在することになる。 人間が想像した瞬間には、宇宙ではすでに想像したものが存在しているのだろうか。してみると、想像力こそ、神にもっとも近い力であるような気がしてならない。 (文中敬称略) うつぼは”海の龍神”?  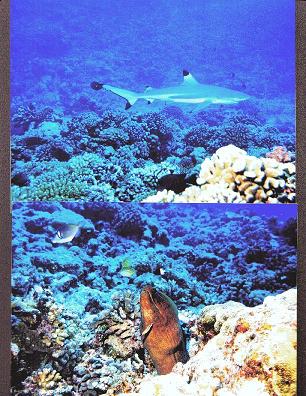 (その6) 超能力者列伝1(西丸震哉) 巷には、自称、他称を含め超能力は多いが、社会的地位のある、あるいはあった人で自他ともに超能力者と認める人は少ない。私が知る範囲では、食生態学者の西丸震哉、画家の横尾忠則、元大阪大学工作センター長の正木和三の三人ぐらいだ。横尾忠則の幽体離脱体験、正木和三のインスピレーションなどは比較的凡人の私でも理解しやすいが、西丸震也の能力は超能力者の中でもかなり“飛んで”いる。 若い人の中には西丸震哉のことを知らない人もいるだろうから、少し彼の経歴について触れておこう。 西丸震哉は1923年9月1日、まさに関東大震災が起きたその日に東京で生まれた。東京水産大学を卒業後、農水省に入り、食品総合研究所官能検査室長を経て1980年に自主退官した。農水省時代に、人間と食べ物との原初的な関係を研究テーマにして、アラスカ、南極、奥アマゾン、ニューギニアなどの秘境を踏査。その体験と研究から、食を通じて人間の行動様式を研究する食生態学を確立した。現代人の食・環境・行動に鋭い警鐘を鳴らし続けている。 私は1980年代に一度だけ、西丸震哉に電話取材したことがある。信濃毎日新聞に彼が書いた「呼びかけたらUFO出た」というコラムを読んで、事実関係を確認したかったからだ。手元にそのコラムがないので正確ではないが、内容は大体次のとおりだ。 「世の中にはUFOを見たという人が大勢いる。そのすべてが地球外惑星の乗物とは限らないだろうが、これだけ多くの人が目撃しているのだから、本当にいるのかもしれない」と西丸震哉は考えた。だが、朝から晩まで空をずっと見ているほど暇ではない。 そこで西丸震哉は空に向かって「私は忙しい身の上なので、UFOが実在するなら、今から一〇分以内に空のこの辺に現われてください」と、テレパシーで呼びかけた(別の本では「なんだってズブの素人たち相手に出てくるんだ。マジメに考えているオレのところに出てきたらどうだ!」と脅したことになっている)。すると次の瞬間、その指定した方角である鹿島槍の右側の空中に楕円形の橙紅色に輝く光体が現われ、稜線を越えて鹿島槍の向こう側へとゆっくりと飛び去っていったのだという。その大きさは、周りの地形と比較すると900メートルはあったかもしれない、と西丸は書いている。 西丸震哉は私の取材に対して、UFOは実在するのだと言って平然としていた。西丸震哉は、不思議なことはなんでも自分で確かめる好奇心旺盛な人物である。幽霊の話、魂の帰宅実験の話、呪いの話、からす天狗の話など彼の著作に詳しい。西丸震哉はそれらをすべて実際に体験しているのだ。(文中敬称略) (その7) 超能力列伝2(西丸震哉) 西丸震哉によるインドから日本への「魂の帰宅実験」は秀逸だ。秀逸というより、かなり変わっている。普通、幽体離脱であれば、意識体(幽体)だけがいろいろな場所へ自由に移動すると解釈できると思うが、西丸震哉の場合は、半分肉体も一緒に移動してしまうらしい。テレポーテーションと幽体離脱の中間といってもいいかもしれない。 それは、だいたい次のような話だ。 西丸震哉がインドに長期間出張することになった。西丸震哉はこの機会に「魂の帰宅実験」をすることを思いつき、出かける前に家族や知人に日時を毎月1回指定してインドから6000キロ離れた東京の自宅に“魂”だけ戻ってみせると約束して旅立った。 第一回目と第二回目の決められた日時には、仕事が忙しくて西丸震哉はすっかり約束を忘れ、留守宅で待っていた家人や知人をがっかりさせてしまった。「これはしまった。今度こそ忘れないぞ」と、第3回目の日時には仕事を早く切り上げ、バンガローに一人でこもって、精神統一を始めた。 初めは外の犬がうるさくて集中できなかったが、4,5回失敗した後、何とか自分の魂(意識体)を日本の自宅に飛ばすことに成功した。ところが日本に飛んだ西丸の意識体は目が見えない。あくまでも雰囲気や感じで自宅の玄関にいることがわかるだけだ。 「ドン、ドン、ドン」。西丸は思い切り玄関のドアを叩く。何も起こらない。そこでスーッと玄関を通り抜けた。さらに、皆が待っていることになっている居間へと向かって、目が見えない状態で歩いていると、膝を思い切り硬いものにぶつけた。普段ならそんなところにモノなど置いてないはずなのに、何があったのか。西丸は膝に痛みを覚えた。そんな痛みに構わず、皆が気づくようにと、便所の木戸をガタピシ動かしてなるべく派手な音を立てるよう努めた。 やがて居間の前までたどりついたのだが、居間には沢山の人がいるような雰囲気がするが、誰がどこにいるのかわからない。このまま居間に入っていくと、怪我をするのではないかと躊躇しているうちに、インドに戻ってきてしまったという。 後日、インドに滞在している西丸のところに報告が届いた。3回目の日時に家人や知人が居間で何が起こるかと待っていると、玄関を叩く音がした。様子を見に行くと誰もいない。しばらくすると今度は、便所の前に置いてあった洗濯機がガタンと音を立てた。その洗濯機は西丸がインドに旅立った後、新しく買ったものだという。次に、便所の扉が誰もいないのにガタピシ鳴る。その後、廊下に誰かいる気配はしたが、そのまま何も起こらなかった――という内容だった。 西丸は見事に「魂の帰宅実験」を成功させたわけだ。玄関をノックしたり、膝をぶつけて痛かったりしたというのだから、半分は魂で半分は肉体であったのだろうか。西丸の体験談にはいつも驚かされる。 (文中敬称略) (その8) 超能力者列伝3(西丸震哉) 西丸震哉といえば、幽霊の話に言及しないわけにはいかない。 1946年に釜石の水産試験場に着任した西丸は、毎晩のように同僚とマージャンをするなどして夜遅く帰宅する毎日だった。ある晩、いつものように家に戻る途中、コンクリート堤の上に腰掛けているうら若き女性がいた。こんなに夜遅く一人で何をやっているのだろうなどと思いながら、通り過ぎて後ろを振り返ると、何とそこにいたはずの女性がいなくなっていた。 それから四日目の晩にも、やはり同じ場所に女性が座っていた。夜間だと寒いにもかかわらず、大きな牡丹の模様のついた浴衣だけのカッコウだ。そして、通り過ぎるとやはりいなくなった。「さては、これは幽霊にちがいない」と考えた西丸は、今度出会ったときは正体を確かめてやろうと、通り過ぎる前に声を掛けてみることにした。 果たして、次の晩も女性は堤の上にいた。西丸はおそるおそる女性に近寄って、「お晩です」と声を掛けた。しかし、女性は反応しない。まるで西丸のことが見えていないようだ。顔を近づけても全く反応がない。よく見ると、非常にきれいな女性で、電灯の明かりの中、顔の薄毛まではっきりと見える。ところが、指で彼女の肩を突いても、突き抜けてしまう。 これはいよいよ幽霊だと確信した西丸は、用意した棒で思い切りその女性をぶったたいた。棒は女性を素通りし、コンクリートにあたり「ガツン」と音が鳴った。何度棒を振り回しても結果は同じだった。根負けした西丸は「もう出て来るなよ」と捨て台詞を残して(本当はすごく恐かったはず)、立ち去るほかなかった。 西丸は心配した。見ず知らずの土地で、自分の前に幽霊が出るのは、その女性が怨んでいる男が自分に似ているせいではないか、と。そこで地元で聞き込みをしたところ、12年前、その場所は入り江になっており、男にふられた27,8歳の女性が身投げしたことがわかった。しかも、死んだ女性が着ていたのは牡丹の柄の浴衣だったという。ただ、安心したのは、その女性をふった男の人相が西丸とは似ても似つかない顔つきだったということだった。 ところが、問題はここからだった。いままで何をやっても振り向いてもくれなかったその女性が、西丸の後をつけて家まで来るようになったのだ。最初は距離が離れていたが、やがて家の中に、そして西丸が寝ている枕元にまで来るようになった。追っ払おうとしても、その女性の幽霊は全く動じない。 あるとき、西丸が寝ていると寒気を感じて目を覚ました。するとそこには、件の幽霊が西丸の顔をのぞきこんでいた。それまでは近くにいても西丸と目が合うことはなかった。幽霊の目は遠くのほうを見つめているようだったからだ。 しかし今回は違った。西丸と幽霊の目と目が合う。幽霊は明らかに西丸の目を見ていた。しかも、ほんの数センチしか離れていない。目が合うと同時に、西丸の体温はみるみる下がっていく。慌てて布団をかぶると、少しは体温が回復するのだが、また目を開けると女性の目と合い、体温を奪われる。西丸は布団の中でまんじりともできないまま、朝を迎えた。 西丸はあせった。「これは大変なことになった。このままでは命が危ない」。そう思った西丸は会社に「これ以上、ここにいるわけにはいきません」と、その日のうちに伝えて、東京に逃げ帰ったのだという(クビにはならなかったらしい)。 そんな釜石での体験から10年が過ぎたある日。大手新聞社の部長の紹介で、前世を見ることができる霊能者がいるから銀座で食事をしながら会ってみようということになった。 その人は女性の霊能力者だった。彼女は西丸の前世を次々と話し出す。西丸はあるときは、アイヌの酋長の息子で、またあるときは唐の時代に活躍した安禄山だった事もあるという。しかし、そんなことを言われても西丸には思い当たる節は全くない。まあ、本当かどうかわからないが、とりあえず乾杯しようとしたそのとき、その霊能力者は「ちょっと待ちなさい」と西丸に声をかけた。「まだ、何か見える」と彼女は言う。「あなたの後ろには牡丹の柄の浴衣を着た若い女性がいる」というのだ。西丸は驚いた。その女性は紛れもなく、西丸が釜石で遭遇したあの女性の幽霊だったからだ。 その女性霊能力者に事情を説明すると、霊能力者はちょっと相談してみましょうと言うと、なにやら西丸の後ろに向かって「モシャモシャ」しゃべりはじめた。やがて西丸に笑顔を向け「もう大丈夫。納得して帰っていったから、もう二度とあなたにかかわりあうこともないでしょう」と言う。 西丸はその後、釜石を訪れる機会があったが、幽霊と再開することもなかった。当時の上司や同僚と、昔の幽霊話をして盛り上がったのだという。 (文中敬称略。もっと詳しく知りたい人は西丸震哉の『山とお化けと自然界』(中公文庫)をお読みください。) (その9) 幽霊と法則 私は顔型のエクトプラズムが写ったいわゆる心霊写真は撮ったことがあるが、幽霊は見たことがない。ただ私の母が、一度だけ幽霊のようなものを見たと言っている。それは次のような話だ。 嵐の夜だった。母が雷の落ちる音で夜中に目が覚めると、鏡台の前に見知らぬ男が立っていた。明治、大正時代のような古めかしい和服姿で、帽子をかぶり、眼鏡をしていた。その顔にはまったく見覚えがない。 その男は、別に母を見るわけでもなく立っていたのだが、やがて前方へと動き出した。幽霊には足がないとはよく言ったもので、歩くのではなく、影像のままスーッと足を動かさずに移動するのだ。 母は当然、驚いた。ところが、手も足も金縛りにあって動かない。その男の影像、つまり幽霊は、母の枕元で一瞬止まったかと思うと、そのまま直角に折れて壁の向こうに消えていったのだという。直角に曲がるとは、何と律儀な幽霊だったことか! 翌日、母のところに親戚が死んだとの電話連絡が入った。ところが母が見た幽霊は、まったくその亡くなった親戚とは似ても似つかない顔立ちをしていたという。 母は懐疑心が強く、あまり幽霊などを信じるほうではないので、昨夜見た幽霊は雷がもたらした放電現象かなにかだと言って、幽霊だと認めようとしない。しかし、断じて夢ではなかったと言う。 母が見た映像は何だったのか。放電現象だとしても、稲光の中に影像を見るとは尋常ではない。雷の光の中に、そのような情報が入っているとでもいうのだろうか。あるいは雷には情報を伝達する媒介としての力があるのか。 その影像が直角に曲がったというのも面白い。そこには何かの法則性を感じさせる。西丸震哉が見た幽霊も、毎晩のように同じ場所、同じ時間に現れたなど非常に律儀だ。 以前、富山医科薬科大学和漢薬研究所の荻田善一教授と話をしていたところ、岡山の方でUFOらしきものを見たことがあると言っていた。驚いて地元に人に「あれはなんですか」と尋ねると、その地元の人は「また出ましたか。その場所にはよく出るんですよ」と言う。ただ、それが何だかはわからず、わかっているのは、「決まって出る」ことだけ。 タイのメコン川では、雨季が終わった10月の満月の晩にだけ、花火のように打ち上がる謎の「龍火」(吉祥姫ホームページ=http://www02.so-net.ne.jp/~masakats/の一ヶ月ほど前の掲示板参照)という、いまだ科学で完全に解明できていない怪現象がある。 母が見た“幽霊”といい、他の超常現象といい、いずれはその法則性が明らかにされるときが来るように思う。 (その10) カラス天狗と話す巫女 西丸震哉が特異な超能力者であることは述べたが、その西丸震哉をして「こいつにはかなわない」「大変な超能力者だ」と言わしめたのが、甲斐の駒ケ岳神社の巫女・柳沢ゑん(故人)だ。 吹雪で立ち往生した甲斐駒ケ岳の山小屋で、西丸はその巫女に出会った。その巫女は山を降りるとき、西丸の心の中をことごとく読んでしまう。しかも、西丸には姿が見えないカラス天狗(刀利天)とも話ができるという。カラス天狗は、だれも知るはずがない配給所に上がってきた品物を当ててしまう。 ここで思い出すのは、義経が出会ったという鞍馬山の天狗や、スピリチュアルカウンセラー江原啓介のカラス天狗の話だ。鞍馬山の天狗の話は義経研究家にとりあえず任せるとして、江原の話は次のようなものだ。 あるテレビ局の取材で江原がスタッフと夜、山道を戻る途中、重い撮影機材を持っているスタッフのために江原はスタッフの足をさすりはじめた。さすってもらったスタッフは、それまでの重たい足取りがウソのように、足が軽くなりヒョイヒョイと歩けるようになった。江原はそれをカラス天狗の力を借りたのだと説明していた。おそらく霊能力者や超能力者には、凡人には見えないカラス天狗が見えるのだろう。 実際、西丸が出会った巫女と江原は非常に似たところがある。山を降りた後、その巫女と西丸の間で次のようなやり取りがあった。 巫女「あんた、お父さんは亡くなったね」 西丸「ええ、昭和19年にみまかりました」 巫女「お父さんの死に目に会わなかったね」 西丸「疎開先で急に死んだもので」 巫女「お父さんが、あんたに言っておきたいことがあるようだから、聞いてあげようか」 西丸「いや、結構です」 その巫女も江原と同様、死者と自由に会話していたようだ。 さらに巫女は、自分の意志で他人の夢の中に出てくることができるという。西丸が写真を送ると約束しておいて、送らないでいると、夢の中で何度も「写真送れ」と出てきたのだそうだ。ただしこれでは、西丸が写真を送っていないという後ろめたさから夢を見たと解釈することもできる。 だが、その巫女のすごいところは、電話のように正確にメッセージを送ることができるということだ。巫女は西丸に大阪に住んでいる男に伝言を頼む。一応、夢で伝えてあるが、住所がわかったら西丸からも伝えておいてくれ、というのだ。西丸はその大阪の男性を探し当て、手紙で巫女の用件を伝えた。すると、先方から次のような手紙が返ってきた。「実はその話ならば以前夢に出てきた白衣のバアさんに言われたことがある。変な夢を見たと思っていたが、事実であったとは大いになる驚きである」 夢を操る人は、おそらく実在するのだろう。アニメ『十二国記』の主題歌の作詞を担当した北川恵子も、他人の夢の中に登場することはやろうと思えば簡単にできると言っていた。もちろん多くの場合は、自分の潜在意識が生み出す夢なのだろう。だが、そうではない不思議な夢もある。 皆さんもそうした夢を見たことがあるのではないですか? (文中敬称略) (その11) ドッペルゲンガー1 ドイツ語で「二重に出歩く者」という意味だというドッペルゲンガー。つまり別の自分(分身)がかってに動き回るという現象は、ただの作り話だと思っていた。しかし、私が取材した人の中にもドッペルゲンガーを見たという人が二人いた。とてもウソをついているとは思えず、「ふ~ん。そのような現象が実際にあるのかな」と思って調べてみると、なるほどゲーテやモーパッサンといった文豪が、自分の分身に出会ったことがあるという。 モーパッサンはある夜、部屋に入ってきたもう一人の自分に出会う。その分身から、当時書いていた小説の続きを聞き、それを書き溜めたのだという。モーパッサンが出会ったのは、未来の自分であったのか。 ゲーテは田舎道を馬に乗って進んでいると、向こうから馬に乗ってやってくる男に出会った。よく見ると、その男はまるで自分ではないか。ただ違うのは、自分が今まで着たことのないような服装であったことだ。もう一度確かめようと振り返ると、その男は消えていた。8年後、同じ小道をゲーテが馬に乗って進んでいるときに、そのときの服装が8年前に出会った“自分”と同じであることに気づき、驚いたという。 西丸震哉も同じような経験をした。西丸は岩塔ヶ原のキャンプ場で夕方、不思議な登山者姿の男に出会う。その男は、西丸たちのテントには目もくれず、20メートル離れた場所をどんどん歩いていく。めったに人が現われない場所と時間なのにこれはおかしい、と西丸は後を追いかけ大声で呼び止めたが、その男の姿は消えてしまった。 それから25年後、西丸が岩塔ヶ原のキャンプ場に再びやって来た。今度、同じやつが出てきたら、正体を暴いてやると思い、その男が出てくるのを待った。西丸はそのときまで、その男のことをこの辺りで遭難した浮かばれない登山者の霊か何かだと思っていたのだ。 二日目の夕方。ふと目を上げると、25年前に出合った男と同じ姿格好をした登山者が現われた。西丸はすぐに突進し、その男の進路上に立ちふさがり、両手を広げ「ちょっと待った! キミ」と叫んだ。ところがその男は、そんな制止には目もくれず、ちょっと下向き加減で西丸に向かってどんどん近づいてくる。帽子を深く被っているため、顔はまだよくわからない。しゃがんで下からその男の顔を覗き込む。ほとんどぶつかりそうなところで、西丸は危ない! と横っ飛びでその男をよけた。 西丸はその男の顔をはっきりと見た。それは25年前の自分であったのだ。右頬には除去する前のホクロもちゃんと付いていた。その自分は、まるで何事もなかったかのように歩いて視界から消えていった。もし、ぶつかっていたらどうなっていたのか。西丸は背筋が凍る思いがしたという。 (文中敬称略) (その12) ドッペルゲンガー2 私がかつて取材した人の中でドッペルゲンガーを見たことがあると証言した人は、一人は画家海後人五郎の奥さんで、もう一人は翻訳家のKさんであった。 海後人五郎は茨城県日立市に住む、かなり強烈な個性をもつ人物である(フリーページの「ETとの交信は可能か」やホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~hutomaki/kaigosyoukai1.htm参照)。私はこの海後人五郎の『毒入り詩』が大好きで、その一部をちょっとここで紹介したい。 じゅげむじゅげむ 遊ばざる者 食うべからず 戯れざる者 寝るべからず 楽しまざる者 住むべからず 笑わざる者 生きるべからず ぱいぽぱいぽ (どうです、面白いでしょう? この調子で反権力の画家海後人五郎は権力者を滅多切りにしていくのです。「働かざる者食うべからず」というのは、支配者が奴隷に対して言う言葉ですよね。海後ワールドのほうがはるかに素晴らしい。) その海後人五郎が自転車で外出しているときだ。奥さんは自宅で留守番していたが、外を見ると人五郎が自転車に乗って帰ってきた。ずいぶん早い帰りだなと思って、声をかけると、どういうわけか黙っている。そして自分の部屋に入っていったようだ。ところがその10分後ぐらいに再び、人五郎が自転車に乗って帰ってきた。 奥さんが「あれ、また外出していたの? さっき帰ってきたでしょう」と聞くと、人五郎はずっと外出したままだったという。では、さっき帰ってきた人五郎は誰だったのか。 Kさんも同じような経験をした。夫が机に向かって仕事をしている姿をKさんははっきりと見たという。ところが、その数分後に寝室から出てきた夫に会う。「あれ、今仕事していたでしょう」と聞くと、いやずっと寝ていたと夫は言う。では、さっき仕事をしていた夫は誰だったのか。 こうした現象はよく、目の錯覚であるとか、他人の空似であるなどとして片付けられてしまう。しかし家の中で見たのでは、他人の空似ではありえない。では目の錯覚であるのだろうか。 目の錯覚説では、西丸震哉のケースを説明できない。西丸と一緒に登山した仲間も西丸の分身を目撃しているからだ。しかも西丸は、至近距離で自分にかつてあったホクロまで確認している。 西丸やほかの目撃者の話を総合すると、どうもドッペルゲンガーは実存する現象であるといわざるをえない。なぜ、そういう現象が起こるのかは推測するしかないが、おそらく強い思いを念じて行動しているときに、その思いが現象化するのではないかと私は考える。たとえば西丸は、何か強い思いを描いて登山をしていたのだろう。そのときの念が強すぎて、念が物質化(あるいは映像化)、つまり自分の分身が生じてしまった。 ゲーテも深い物思いにふけりながら、馬に乗っていたに違いない。それが時間を超えて8年前の過去に影像となって現出した。Kさんの夫も、寝ながら仕事をしなくてはと強く念じたため、それが影像となって現われた可能性がある。海後も早く家に帰りたいという思いが実態化したのかもしれない。そういえば、想念が実態化してしまう『禁断の惑星』というSF映画が昔あった。 強い念がドッペルゲンガーの正体ではないだろうか。しかもモーパッサンのケースにしても、ゲーテのケースにしても、西丸のケースにしても、未来や過去へと時間を超越して現われるところが面白い。まるで想念が時間を自由に移行した、つまりタイムトラベルしたとしか思えない。 実はここに、ドッペルゲンガーやデジャビュの謎を解く鍵がある。(文中敬称略) (その13) 時を超越する想念 私はあまり不思議な経験をしたことがないと書いたが、唯一デジャビュ(既視感)現象については、子供のころから確信していることがある。デジャビュとは、行ったこともない場所なのになぜか行ったことがあるように感じたり、ある場面がすでに見たことがあるように感じたりする現象。単なる錯覚ではないかとする向きもある。 しかし、これは断じて錯覚ではない。それは私の経験からそう断言できることだ。 結論から言おう。デジャビュ現象が起きるのは、時空を超越して想念が“共鳴”した場合に起こる。人間は過去を思い出す。ところが時々、未来の想念(あるいは過去生の想念の可能性もある)が入ってきてしまうことがある。そのとき、何とも言えない不思議な感じを覚える。 音叉が、距離が離れていても共鳴するように、時間を越えて想念が共鳴現象を起こすのだ。それは未来の想念が現在に入ってきて共鳴する場合もあれば、今生の記憶ではなく過去生などの想念が現在に入ってきて共鳴する場合もあるようだ。私の場合は前者である。 あの何ともいえない奇妙な感じ。私はそれを経験した何年か後に、同じ奇妙な感じを思い出すことから、過去の時点で今の気持ちと共鳴したために、あの時奇妙な感じがしたのだなと理解できるわけだ。つまりゲーテが8年後に、あのときに馬に乗ってすれ違ったのは自分であることを発見したときの気持ちと同じである。言葉ではこれぐらいでしか説明できないが、感覚的には100%、その現象を理解している。 このことから何が言えるか。一つは、時間は“同時”に存在しているということだ。私は、時間が過去から未来へと一方向に流れているとは思っていない。実は、時間は未来から現在、現在から過去へとも流れる。言い方を変えると、過去と未来と現在は同時に存在している。だからこそ、過去や未来の想念が現在の私の中に入り込んでくる。 そして最も大事なことは、現在を変えれば未来だけでなく過去すら変えることができるということだ。そうでなければ、私たちが「今」を生きる意味もなくなってしまう。 (その14) アトランティスの記憶1 この世界には、アトランティスの“記憶”を持つ人がいる。「そんな、まさか」と思うかもしれないが、信じられないほど大勢いるのだ。しかも克明に当時のことを覚えているため、アトランティスが存在したことを否定するのは難しくなってしまう。 中でも、以前紹介した正木和三(故人)の体験には、思わずうなってしまう。正木は大阪大学工学部工作センター長を務め、定年退職後は岡山のバイオベンチャー企業「林原」の生物化学研究所で新製品の発明・開発を担当した理科系の発明家だ。精神世界関連の本も多数書いている。 私が正木和三を取材したのは、1986~87年ごろ。当時はゴルフでエージシュート(自分の年齢かそれ以下のスコアでラウンドを回ること)を達成したからといって、ご丁寧にテレホンカードをいただいたこともある。 正木和三は私にアトランティスに関する不思議な話をしてくれた。その話によると、正木和三は小学生の頃から毎月1度、必ず同じ夢を見続けた。どこの場所かはわからない石畳のある町の風景だった。その道の脇には全く透き間のない石組みが延々と続いていた。正木和三にとって心当たりはまったくなく、「不思議な夢を見るものだな」と思わずにいられなかった。 ところが1970年ごろのある日、何気なくテレビを見ていると、何と夢とまったく同じ風景の映像が目に飛び込んできたではないか。それは、米国・フロリダ沖のバハマ諸島ビミニ群島近くで、1968年に発見された奇妙な巨石の構造物らしき海底遺跡を撮影した影像であった。 正木和三は驚いた。さらに不思議なことに、それまで四〇数年間続いていきた毎月一度の不思議な夢が、その日を境にぷっつりと途絶えたのだ。 その海底の遺跡というのは、約1・2キロ続くJ字型の巨石道路や長さ100メートル、幅10メートルの石の壁などでできた遺構らしきもので、一部の考古学者の間でビミニロードと呼ばれ、水没した古代の遺跡ではないかとして格好の研究対象となった。 一体、これらの遺跡と思われるものは何なのか。ただの自然の造形によるものなのか、あるいは人類がまだ知りえていない古代巨石文明の建造物の一部なのか、多くの研究家が実地調査をするために、ビミニ群島を目指した。 (その15) アトランティスの記憶2 ビミニ群島の海底遺跡は、学術調査とは別にある研究家たちの注目を集めた。というのは、それより28年前の1940年に、エドガー・ケイシーというアメリカの“超能力者”が「アトランティスの首都・ポセイディアが再び浮上する。1968年か69年に予期されている。そう先のことではない」という内容の予言をしていたからだ。 しかもその場所については、「フロリダ海岸沖のビミニとして知られるところに近い海底の泥土の下から、かつて大陸の最高所であったポセイディアの神殿の一部が発見されるだろう」と1933年に明確に指摘していた。 ケイシーが詳述したアトランティスについては後述するとして、正木和三はこれをきっかけにして、自分はもしかしたらかつてアトランティス人であったのではないだろうかと思うようになった。そのときすでに正木和三は、宇宙の「高次元生命体」からインスピレーションを得て、過去何度も日本で生まれ変わり(転生)をしていたことを知らされていたからだ。輪廻転生が事実で、アトランティスが伝説だけの大陸でないなら、自分が過去生においてアトランティスの住人であったとしても不思議ではない、と考えた。 それから十数年経った1986年10月16日。その考えをさらに決定的にする出来事が起きた。その日、正木和三は全く見ず知らずの二人の外国人の突然の訪問を受けた。 アメリカ人の学者と企業コンサルタントらしく、二人は正木和三に会うなり、「あなたこそ、この石の持ち主に違いない」と言って、直径四センチほどの奇妙な円盤型の石を手渡した。それはキュウリを輪切りにしたような色と模様をした、メノウに似た宝石のようだった。 正木がその石を手に持つと、手のひらの中で熱くなった。そして、その石が正木の元にまで届けられたいきさつをその二人から聞かされたとき、「こんなことがありうるのだろうかと狐につままれた気持ちになった」と、正木は言う。 (その16) アトランティスの記憶3 二人の訪問者が明かしたいきさつは、にわかには信じられないような話だった。それは次のようなものだ。 二人は来日する一年ほど前にエジプトへ行ったときに、まったく思いがけなくエジプトの神官と名乗る人物に出会った。その神官は二人に歩み寄ってきて、手に持った不思議な石を見せながらこう言った。「この石は6000年も昔からエジプトの神官が受け継いできたものだ。あなた方は近いうちに日本に行き、必ずこの石の持ち主に会うことになっている。これをその人に渡してください」。そして神官は、その石を二人に手渡した。 二人は驚いた。そのときは別に日本に行く予定もなかったし、誰だかわからない人間に一体どうやって石を手渡したらいいのか見当もつかなかった。だが、その神官が「石の持ち主は必ずわかる」と言い張るので、石を預かったという。 そうしたら本当に、仕事の都合で日本に行くことになり、二人は何かに導かれるようにして正木和三にめぐり合った。そして会った瞬間、直感的に「この人が持ち主だ」と思ったという。 その石は何なのだろうか。エジプトの神官は6000年前から受け継いできたと言ったほかは、石について詳しくは教えなかった。そのため正木も、その石を手渡した二人も、何の石なのか知る由もなかった。 ところが、その後間もなく、さらに驚くべきことが起きた。正木和三がその石の話を講演会で話したところ、参加者の一人が突然、感極まって泣き出したのだ。その人は女性で、正木が「どうしたのかな」と訝っていると、その女性はにわかに、周りの人が誰も理解できないような言語で正木に向かって喋りだした。 その場にいた誰もが、それまで聞いたこともないような言語だった。そう誰も・・・。正木以外は。 不思議なことに、正木にはその言葉の意味がはっきりとわかったのだ。正木もつられるように無我夢中で同じ言語をしゃべりはじめた。もちろんそのときまで、正木はそのような言語を聞いたこともなければ、話したこともなかった。同時に頭の中では、その言葉を完璧に理解していた。 周りの人は皆、唖然とするしかなかった。正木が後に解説するには、その女性はその石がアトランティスの神官が持っていた聖なる石で、正木がその神官だったとアトランティスの言葉で話したのだという。そしておよそ1万年以上の時が過ぎ去り、神官の石は巡り巡ってかつての持ち主である正木の手元に返ってきた。実はこのように玉が持ち主に戻ることを「完璧」というのだ、と正木は言う。 (その17) アトランティスの記憶4 正木和三の驚異的な体験を理解するには、二つの可能性について言及しなければならない。一つは、アトランティスは実在したのか、実在するとしたらどのような文明を持ち、どうなってしまったのか。二つ目は、輪廻転生がありうるのか、という問題だ。 今から1万年以上も前に、アトランティス大陸があったなどというと、たいていの歴史学者や考古学者は笑い出すにちがいない。ましてや、正木和三のように「私は当時、神官でした」などという話は、信じろといわれても無理というものだ。 にもかかわらず、そんな幻の大陸が今日までなお、ロマンと謎をもって実在したかもしれないとして議論されるのは、紀元前350年ごろ、ギリシャの哲学者プラトン(紀元前427?~同347年?)がエジプトの神官から聞いた話として、『ティマイオス』『クリティアス』という対話篇に書き記していたからだ。対話篇自体は、ソクラテスと3人の友人が架空の問答を交わす形式で書かれている。 その対話篇では、プラトンの母方の祖父に当たるクリティアスがその祖父の大クリティアスから子供のころに聞いた伝説として、アトランティスが登場する。大クリティアスが父親のドロビデスから聞いたという伝説で、そのドロビデスもまた、友人のソロン(紀元前640ごろ~同560年ごろ)から聞いている。ソロン自身は、エジプトのサイスで太古の記録文書を保管する神殿にいた老神官からアトランティス伝説を聞いたのだという。 まるで秘伝ように語り継がれてきたその伝説によると、紀元前1万年ごろ、ジブラルタル海峡の外側、すなわち大西洋の彼方に北アフリカと小アジアを合わせたよりも大きいアトランティスという名の島(大陸)があった。アトランティスは周辺の島々だけでなく、エジプト以西のリビアやトスカナ以西のヨーロッパをも勢力下に置く大帝国を築き上げていた。首都の中心には王宮と海神ポセイドンを祭る神殿があり、神殿は黄金、銀、象牙、そして炎のように輝くオルハリコンと呼ばれる謎の金属で飾られていた。 アトランティスは全部で10の王国に分かれ、それぞれの国を統治する10人の王たちは、ポセイドンと人間の女であるクレイトーとの間に生まれた五組の男子の双子の子孫であった。王たちは、アトランティスという名の由来ともなったポセイドンの長男アトラスの一族を宗主としてそれぞれの国を治めていた。 アトランティスの人々は初め、神の心を持ち、美徳を重んじ、物欲を軽蔑していたらしい。ところが、世代を重ねていくうちに神性が薄められ、人間の気質が優位を占めるようになり堕落。よこしまな欲望に染まり、力の誇示を始める。やがてヨーロッパ全域を蹂躙しようと侵略を開始した。 これを見た神々の王ゼウスは、堕落したアトランティスに罰を下そうと考え、すべての神々を最も尊い殿堂に集めた。 ゼウスがこの会議で何を言ったかは、プラトンの対話篇がここで唐突に終わっているためわからないが、いずれにしても、プラトンが対話篇の別の箇所で述べているように、恐ろしい地震と洪水などの異変によって、アトランティスは海中に没したのだ。そして、ヨーロッパとの大戦争の記録がエジプトの古文書に残され、ソロンの知るところとなった。 (続く)=文中敬称略 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|